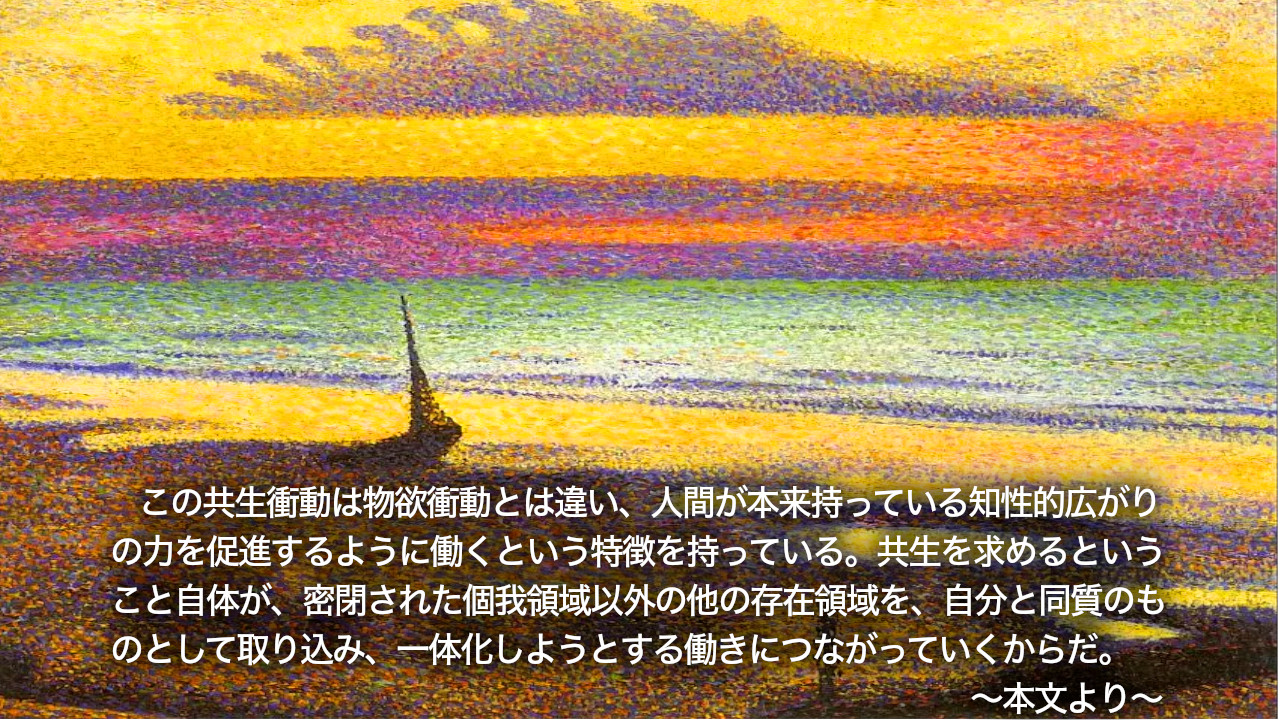~「共生衝動」が生み出す新しい価値世界~
「物欲衝動」が今の金銭至上の価値共有世界を生み出しているとしても、人間の中には「物欲衝動」以外に、もうひとつの根本衝動として「共生衝動」が存在している。
この共生衝動は、物欲衝動とは違い、人間が本来持っている知性的広がりの力を促進するように働くという特徴を持っている。共生を求めるということ自体が、密閉された個我領域以外の他の存在領域を、自分と同質のものとして取り込み、一体化しようとする働きにつながっていくからだ。共生衝動自体が、個我意識を超え他の領域の広がりへと向かおうとする志向性を本来的に持っており、それが対象を観察し、認識し、意味付けし、価値付けし、同化しようとする知性の働きと融合するからである。
共生を求める力とは、ただともに生きようとするだけではなく、ともに生きようとするものを、自分にとっての大切な要素として取り込んでいく意識の力であり、それは人間どうしの関係に向かうだけではなく、他の生命との関係、まわりの自然との関係、さらには地球や、宇宙との関係に向かっての知性的広がりを作っていく。つまり、共生衝動とは、人間の意識を「より大きな、豊かな、深い、知的なもの」に向かって育てるための母体として存在していると言うこともできるのである。
経済至上の個我の物欲だけが本質である世界では、「より大きな、豊かな、深い、知的なものに向かって育っていく自己意識構造」とはどういうものなのかという、その視点自体が生まれてこないのである。その視座の広がりは、共生を求める世界でこそ、初めて可能となるものなのである。
このような、共生を求める人間的資質を持ち、たがいに理解しあい、支え合って生きることが人間にとってもっとも価値あることだという高度な価値意識と上質の衝動性を持っている人々が今の時代の中に存在しているとすれば、まずはこの人々が少人数でもいいから各領域で集まり、価値共有の文化的な集団を作るべきである。
同質の衝動性と価値意識を持った人々が集まり、同じ価値評価表をたがいに共有しあい、ひとつの集団世界を形成することで、その価値評価表に記された通りの現実世界が、具体的に生み出されていくというメカニズムは、確実に存在している。価値評価表の上位に置かれた価値項目は、その集団全体によって守られ育てられ、現実構成要素として具体化されていく。それとは逆に、価値の対象とならないものは、その集団世界においては縮小し、消去されていく。
たとえば「共生」が高い価値を持っている集団世界では、そのための具体的システムが考案されたり、共生についてこれまでに研究された著作等が再評価され多数の人によって読まれ、その研究がさらに進んでいったりする。あるいは、仲間一人ひとりの経済的困窮を全体として解決するシステムが、試行錯誤を繰り返しながらも、堅実なものとして育っていく。
同時に一部の富裕層や特権階層を生み出す構造自体は否定され、格差社会や差別意識を助長するような文化や「考え方」自体が消えていく。そして、自分だけの利害を求める我欲的行為は、それが結果的にどんなに巨額の資産を生み出すものであろうとも、否定の対象となっていく。
経済という項目が最高位に置かれた価値評価表の共有で成り立っている今のこの世界、人間が経済的価値で分別され、人間的価値と金銭的価値が完全に同化してしまった今のこの異常な世界、そこから離脱するためにこそ、「共生=ともに生きること」に最高の価値をおいた価値共有の集団世界を、新たに生み出していくべきなのである。
同じ価値観と同質の根本衝動を持った人間どうしが、たがいの価値評価表をたがいに共有し合い、ひとつの集団を形成し、その世界でともに生きていこうとすることで、その価値評価表に描かれたとおりの世界が現実的なものとして生み出されてくるということは、実は予想している以上にすごいことなのだ。この現象は、小さな集団の世界においても、大きな集団の世界においても、ともに生じる普遍的な現象である。
~集団世界が人間の進化をうながした~
「共生」という理念や、「ともに生きる」というその考え方に価値を感じていたとしても、しかし「集団を作る」というこの行為に対して、今の時代を生きる大半の人々が、ある種の違和を感じているのは事実である。それは私たちが経済至上の価値世界を、あまりに長い間、生き続けているせいである。
経済至上の価値世界において、常に私たち一人ひとりは、「人間的価値」ではなく「経済的価値」によって評価され続け、経済効果、つまりお金を生み出す力を持っているかどうかという尺度で常に値踏みされ続けてきた。その結果、人と人とのかかわり合いに対して、心の深い部分で、常に強いストレスや疲労感を感じるようになっている。社会のいたるところに潜む「経済的恐喝者」という目には見えない存在に常に脅され続け、人間と人間の関係世界に対して、容易には癒やすことのできない重い疲弊感を、感じるようになってしまっているのだ。
だから他人たちからは距離を置いた自分だけ(あるいは自分たち家族だけ)の隔離された生存空間で、自分、あるいは自分たち家族だけの安定した経済生活を守ることが最良の生き方であるというのが、今の時代を生きる人々にとっての、もっとも一般的な生存感覚となっている。そのために、他の人間たちとともにひとつの集団世界を作るということが、宗教じみた不自然な行為としてしか感じ取られなくなっているのだ。
今の時代を生きる人々が、どんなに集団を作ることに対して違和を感じようとも、しかし人間という生物が、これまでも述べてきたように、集団性の生物として進化を得てきたということは、否定できない事実としてある。そのことを端的に示す「社会的知能仮説」というひとつの考え方がある。
人間が集団を形成し、たがいに助け合い、意志を伝え合いともに生きようとするそのプロセスを通じて、思考を担う脳が大きくなり、人間を進化させてきたという考えだ。つまり私たち人間は、「人間としての意識、心」を、「集団世界」を生きる必要性から生み出してきたということになるのだ。悲しみや喜びや怒りや愛等の感情も、人と人とのかかわり合いやつながり合いの中から生まれてきたものであるし、回りの人間たちとの関係を受け止め、回りの人間たちとたがいに意思疎通する必要性から、複雑な感情や意識の働きも育っていったと考えることができる。
集団世界を土壌として、私たち人間としての「意識、心」が育ってきたのであるとすれば、私たちの心、精神、自己意識を、より優れたものに向かって成長させていくためには、それを可能とするだけの質をもった集団世界を、私たちみずからが自覚的に作り上げていく必要がある。
「経済」至上の価値共有の集団世界が、いかに人間の心、意識を委縮させ、たがいを孤立させ、退化させていくかという事例について、これまで何度も述べてきた。「経済」という価値項目にかわって、人と人とがともに支え合い、ともに生きていくという「共生」にこそ価値を置いた共有世界を生み出していくことで、今の人間とは違う、新しい質を持った人間が生まれ、育ってくることは、確かなことなのである。
~「衝動」を自覚的に育てることは可能である~
人間の中に存在している2つの根本衝動、「物欲衝動」と「共生衝動」というこの2大衝動のうち、「共生衝動」を生存の基盤として世界を生み出していくというその生き方自体を、人間は長い間、放棄し続けてきた。
本来は「共生衝動」をみずからの根本衝動として持っている資質の人間たちでさえ、「物欲衝動」を基盤にした今のこの世界にさらされながら、その衝動の質自体を、変質させ続けている。今人間たちが生み出し続けているこの世界自体が、広告、メディア、ビジネス、流行、風潮、文化現象にいたるまで、物欲衝動を刺激する装置に満ち満ちているからだ。広告や流行は常に私たちの購買衝動を刺激し、ビジネスや商業主義的文化や政治は、「経済的、物質的豊かさの追求こそが人間の幸福の本質である」というマインドコントロールで、たえず私たちの物欲衝動を煽り続けている。
「衝動」とは、恒常的に刺激され続けることでより強いエネルギー値を持ったものへと育っていき、逆に放置され続けると、次第に萎縮していくという性質を持っている。これら「衝動の特性」について、ニーチェが興味深いアフォリズムを書いている。
われわれの自由になること。
『曙光』
われわれは園芸家のように、自分の衝動を思いのまま処理できる。そして知る人は少ないが、怒りや、同情や、思案や、虚栄心などの芽を、格子垣の美しい果実のように実り多く有益に育てることができる。われわれは園芸家のよい趣味に従っても悪い趣味に従ってもそうすることができるし、またいわばフランス風にも、イギリス風にも、オランダ風にも、シナ風にもそうすることができる。
われわれは自然の思いのままにさせて、あちこちを少しばかり飾ったりきれいにしたりして面倒を見ることもできる。われわれは最後にまた、一切の知識や考慮を持たずに、植物をその自然のままの恵みや障碍の中で成長させ、お互いの間で相闘わせることもできる。それどころか、われわれはそのような野生状態に喜びを抱き、たとえそれが手に負えなくなっても、ほかならぬこの喜びを抱こうとする。このすべてのものがわれわれの自由になる。
しかし、これがわれわれの自由になるということを一体どれほどの人が知っているのか? 大抵の人たちは自分のことを完全に成長し切った事実であると信じてはいないか? 偉大な哲学者たちは、性格は変化しないという学説でこの偏見をさらに確証しはしなかったか?
個々の人間の中に多数存在する「衝動」を植物にたとえ、それらの成長の様相を庭園の造形や野生状態の繁茂になぞらえながら、ニーチェは「衝動」が持つ特性について、ここで展開している。園芸家の造園のように、自覚的に意図的に諸衝動を秩序だったものへと育てることもできるし、野原における植物の繁茂のように、衝動を野生状態のまま放置し、自然発生的に育っていくそのあり方に感動を覚えることすらできる。
ニーチェ自身は高貴さと野獣性とがともに同居するギリシャ貴族の精神のあり方を理想にしており、このアフォリズムの中でも、野生状態で育っていく衝動のあり方を肯定的に見ているのが分かる。物欲衝動も、経済至上の価値世界の中で、ある意味、野生状態のまま肥大し続けてきたということができる。
しかし同じ野生状態に置かれた衝動であるとしても、ギリシャ貴族の知的精神性の中で育つ野獣性=自然性としての衝動と、金儲けのためにしか生きる意味を見いだせない卑しい俗衆本能としての物欲衝動と、その両者には明確に質的な違いがある。ニーチェが理想とするギリシャ貴族的人間像をどう評価するかは別にして、このアフォリズムで学ぶべき重要なポイントは、個々人の中に存在するいくつもの諸衝動の成長や縮小や再配列が、衝動の本質的性質に自覚的になった人間にとって自由になるというそのメカニズムについてである。
我々の中にある良質な衝動も破壊的衝動も知的衝動も卑しい衝動も、野性的衝動も、そのどれを成長させ肥大させ、あるいは縮小させ、退化させていくか、そのすべてが「われわれの自由になる」ということなのだ。
ニーチェはそこまでは語っていないが、われわれの中にある諸衝動を自由に自覚的に育て上げていくためには、ある一定の条件は必要となってくる。それは同じ質の諸衝動を持った人間たちがその諸衝動によって生み出される価値評価表を共有しあいながら、ともに同じ価値世界を生きるということだ。
そのことによって、価値評価表を根底で生み出している諸衝動は常時刺激されより強いものへと育っていき、価値評価表から外された価値対象とその基盤にある衝動は無視され、あるいは拒絶され、より弱いものへと萎縮していく。これらのメカニズムを通して、人間としての質それ自体が変革され、新しい人間の型がその集団世界そのものとして生み出されてくるのだ。